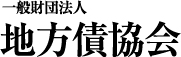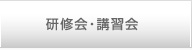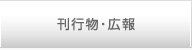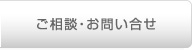>>�������������@ >>���̒����@ >>���C��E�u�K������@ >>���y�E�[�������@�@>>���̑��x������
| �N�@�x | ���������e�[�}�E���e |
|---|---|
| �ߘa�U�N�x |
���킪���ɂ�������Z���̕ω��ƒn���̌l�����~�����Ɍ������W�]��
�@���{��s���}�C�i�X�����Ȃǂ̋��Z����̘g�g�݂̌��������{�������Ƃɉ����A�ꌘ���č��o�ςɔ����~����ł̐��ڂ�A�A���������N�_�Ƃ��镨���㏸���͂Ȃǂ̕����̏�U�ꃊ�X�N�ւ̌��O����A�����̒lj����グ�ւ̎v�f�ɂ��������㏸���Ă��܂��B |
| �ߘa5�N�x |
<�n���s��ɂ�����ESG�����A�f�W�^���،������̊��ω��ւ̑Ή�>
�@SDGs��E�Y�f�ւ̊S�́A2006�N�̐ӔC���������ɂ����āA�����ӎv����v���Z�X�̊ϓ_�̈�Ƃ���ESG���g�ݍ��܂ꂽ���Ƃ��_�@�ɁA�}���Ɋg�債�Ă��܂��B�O���[���{���h�������̃K�C�h���C������������A���ۋ��Z�@�ւ����S�ł������O���[���{���h�̔��s�̂́A���{���ʊ�ƁA���Z�@�ւɂ�������L���A�{�M�̒n���c�̂ɂ����Ă��A2017�N�̓����s�ɂ��O���[���{���h�N���_�@�Ƃ��āA�O���[���{���h�𒆐S��SDGs�̋N���傫���������Ă��܂��B |
| �ߘa�S�N�x |
���s����̕ω��ǖʂ������Ƃɗ^����e���Ɠ����j�[�Y�𑨂����n���ɂ�����I�Ȏ������B�̌�����
�@�R���i�Ђ���̌o�ϐ��퉻��V�A�̃E�N���C�i�N���ɂ��n���w�I���X�N�̍��܂��w�i�Ƃ�����������A�����㏸�A�������i�����Ȃǂ���A���Ď�v���𒆐S�ɃC���t������}���ɍ��܂��Ă���A���Ċe���̒�����s�͋��Z�����]�����A���Z�����߂ɓ����Ă��܂��B����ŁA���{��s�́A����I�E�����I�Ȍ`�ł̕�������ڕW�̎�����ڎw���A�C�[���h�J�[�u�E�R���g���[��(�x�b�b)�𒌂Ƃ����ɘa�I�ȋ��Z������ێ����Ă��܂��B�����������A�䂪���̒n���s����݂�ƁA�����Ēꌘ�������Ǝ��v�Ɏx�����Ă�����̂́A�㏸��ɂ���C�O�����̌��ʂ��⍑���̋��Z�����ύX�ւ̎v�f�̍��܂�Ȃǂɂ���ĕs�������𑝂������������C����A�s��̒n�����͈������Ă��Ă���A�ꕔ�̓����Ƃɂ����Ă͍������ɐT�d�Ȏp�������������܂��B |
| �ߘa�R�N�x |
���n���s��̊��ω��̓_���Ɣ��W�Ɍ����������`�ʔ��s�Ƌ������s�̔�r�܂��ā`��
�@�n���c�̂̎�v�ȍ������B��i�̂P�ł���n���́A�ǍD�Ȋ��ł̔��s�������Ă��܂��B�䂪���̋��Z�s��́A2020�N�����̐V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̊g������A���{����{��s�ɂ���������E���Z��������w�i�ɁA���肵���������Ă���A�����������A�䂪���̒n���s����݂�ƁA�ꌘ�������Ǝ��v�Ɏx�����A�n���c�͈̂��肵�Ēᗘ�ł̎������B���p�����Ă��܂��B |
| �ߘa�Q�N�x |
���V�^�R���i�E�C���X�����NJg��̉e���܂����n�������c�̂̎������B���@�ƒ��B���̐����ɂ��ā�
�@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ����E�I�Ɋg�債�A�e���̋��Z�s��͈ꎞ�I�ɑ傫�ȕϓ��Ɍ������܂������A�����Ƃł͊e�����{�⒆����s�ɂ���K�͂ȍ�������E���Z����ɂ��A�S�̂Ƃ��ė������������߂��Ă��܂��B�����������A�킪���̒n���s����݂�ƁA�����Ēꌘ�������Ǝ��v�Ɏx�����A�n�������c�͈̂��肵�Ēᗘ�Ȏ������B���p�����Ă��܂��B |
| �ߘa���N�x |
���n���s���������ω��ƈ���I�E�����I�Ȏ������B�̎����Ɍ����ā`��s������ɂ�钲�B�𒆐S�Ɂ`��
�@���{��s�̋��Z�ɘa����ɂ��A���Z�s��ł͒�ʂȋ����������b���p�����Ă���A��s�������ʁA��������̌p���������܂�钆�A�n�������c�͎̂������B�R�X�g�̖ʂŒ���������������A�����ƁE���Z�@�֓��͎�������E�^�p���v�̌����ɂ��A���������v���ɒu����Ă���܂��B |
�@�u�n���v�͊u���Ŕ��s���A�n�������c�́A���Z�@�y�я،���Г��̉�����݊ԕ��тɍ����̑��W�c�̂Ƃ̌𗬂̏�Ƃ��Ă����p�����������߁A����y�ъW�@�֓��ɍL�������Ŕz�z���Ă��܂��B�f�ڂ�����e�́A�ŐV�́u�n���Ɋւ���_���v�A�u�n���v��E�n�������v��E�������Z���v�擙�̉���v�A�u�n�������u���E���Z�u���v���𒆐S�ɁA�^�C�����[�ȋ��Z�A���Ѝ֘A���A�n��o�ς̏��ƂȂ��Ă���܂��B�܂��A�n��̊������Ɏ��g��ł���W�҂̕A���y�̖��Y�A���j�����Љ�A����ɁA���̑������Ƃ��āA�s���{���y�ѐ��ߎw��s�s�����s����n���̌��ʖ����ꗗ�A�c�̕ʔ��s�z���̏ڍׂɂ��Čf�ڂ��Ă���܂��B
�@�n������ł́A�n�������c�̂ɂ����āA���Z�E�o�ϊ��̕ω��ւ̑Ή����]�O�ɂ������ċ��߂���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ܂��A�n�����x�A���Z�E�o�ς̓������Ɋւ�����e�𒆐S�Ƃ����s�����ɂƂ��ĎQ�l�ƂȂ�������u�G���@�s�����ւ̒n�����v��N�S�s���A�S���̎s�����ɖ����Ŕz�z���Ă���܂��B
���̑����s���̔��s
�n������́A�n�����s���̒n�������c�̂ƁA���̋�s�E�،���Г��ɂƂ��ĕK�v�ȏ������ꂼ��ɒ��A���邢�͑��݂̏��̌����𒇗������邱�Ƃɂ���āA�n���̈��肵�����s�Ɖ~���ȏ����̑��i�Ɏ����邱�ƂƂ��A���̂悤�Ȋ��s��������y�ъW�@�֓��ɍL�������Ŕz�z���Ă���܂��B
���̔N��́A�n�������c�̂����N�x�����Ȃɒ��Ă���f�[�^�̒��č쐬���Ă���A��ȓ��e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B
���n�����s�i�\��j�z�̏@���n�������̎ؓ��E���s�@���n�����ݍ��̏�
���n���֘A�o�ϓ��v�@�����Z�E���Ѝ��@���n�������c�̂̍�����
�n���֗�
������ɂ����܂��ẮA�n�������c�̂��،��Ŕ��s����n���̔��s�v�������}�C�N���t�B�����ECD-ROM�Ɏ��^�E�ۑ����Ă���܂����A����̊F�l�̌����̗��ւ�}�邽�߁A���s�����E���s���i�E�\�ʗ����E���Ҋ����E���s���E���s�z�Ƃ����̃t�B�����i���o�[�ECD-ROM�i���o�[���L�ڂ����A�u�n���֗��v�s���Ă���܂��B
�n�����̑���
�@�n������ł́A�s���{���A���ߎw��s�s��������������f�[�^�����ƂɁA���̏���Ƃ��āA��������ɖ����Œi���[���Łj���Ă���܂��B
���n�����ʔ��s�����E�،��R�[�h�ꗗ
���n�������ʔ��s��
����s������n���̔��s�E�ؓ��̏�
���s�����E��s������n���̔��s�E���ҁE���ݍ��̏�
���ꎞ�ؓ����̏�
�����̑��̊֘A���
�n���֘A���̃l�b�g���[�N�T�[�r�X
�z�[���y�[�W
���̏���n������̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��A����ɒ��Ă���܂��B
�@������̎��ƊT�v(�����������ƌ��ʂ̎�v�T�v�A���C��E�u����̂��m�点�A���s���̈ē��Ȃ�)
�A�s�����n���̔��s�����y�є��s�c�̕��тɒn�������E���s�z�E�c���E���s�\��z
�B�s���{���A���ߎw��s�s�̍�����
�C�n�������c�̌������Z�֘A���
���ȏ�̑��A�n�������c�̂Ɍ����āA�n���ɂ�鎑�����B������̊Ǘ��E�^�p���ɗL���ƂȂ���s��̓��������A�����ƂɌ����āA�n���̔��s����(�\��܂ށB)��n�������c�̂̍������̏����f�ڂ��Ă���܂��B
�n�����[���}�K�W��
�s�����n���̔��s�����̏�����[���ɂ�葦��������ɔz�M���Ă���܂��B
�@���N�x�̒n���̓��ӓ���⎖���葱�����̂ق��A�n���Ɋ֘A���鏔���ɂ��Ă̎��m��}�邽�߁A�����Ȃ̋��͂āA���N�t�ɑS��7�u���b�N�ōu�K����J�Â��Ă���܂��B
�@�s���{���A���ߎw��s�s���̒S���҂�ΏۂɁA���Z�@�֓��̋��͂đS���^�s�����n���̔��s�����Ɋւ��錤�C����A���N�V���ɓ����łQ���Ԃ̓����ŊJ�Â��Ă���܂��B
�u�Z���Q���^�s�����n�����C��v�̊J��
�@�u�������B�̑��l���v�̎�@�Ƃ��āA����13�N�x�ȍ~�A�e�n�������c�̂ł̎�g�݂����������Ă���Z���Q���^�s�����n���̔��s�x�����тɔ��s������Љ���Ƃ��āA�����ȂƂ̋��Âɂ��A���C����J�Â��Ă���܂��B
�@���N8���ɓ������A9���ɕ��ɉ��ŊJ�Â��A���s�c�̂ɂ��̌��k���̕��s���Ă��܂��B
�@�n�������c�̂̒n�������S���ҋy�ы�s�E�،���Г��̌����S���҂�ΏۂɁA�n���ɌW�铖�ʂ̖��_�A������̎戵�y�ы��Z�o�Ϗ���ɂ��Ă̒m�����K�����邽�߁A���N�H�ɑS��7�u���b�N�Ō��C����J�Â��Ă���܂��B
�u�n���s�����E���Z�u����v�̊J��
�n���s�����y�ы��Z�o�ς̓��ʂ��鏔���ƍ���̉ۑ蓙���e�[�}�ɁA�����ȁA���{��s�̊������u�t�ɏ����A�n�������c�̋y�ы��Z�@�֓��̊����E����ΏۂɁA���N�S��2�J���ōu������J�Â��Ă���܂��B
�@�n�����܂߂��n���������x�̊T�v�ɂ��Ă킩��₷��������A�e���W�҂Ƃ̑��ݗ����Ɏ����邽�߁A�p���ɂ�鏬���q�����쐬���Ă��܂��B�n���̊T�v���ȒP�ɂ܂Ƃ߂��p���p���t���b�g�Local BondSystem in Japan��y�ђn������̋Ɩ����Љ���About Local Government Bond Association��́A������͂��߁A�O������̎��@�W�ҁA�ݓ��O�����Z�@�֓��ɖ����Ŕz�z���Ă���܂��B
��ʍU���x�ɌW�鎖��
�n������ł́A����18�N1������J�n������ʍU���x�̉~���ȉ^�c��}��Ƃ����ϓ_����A�s���{���E���ߎw��s�s�E�s�撬���E�ꕔ�����g���ւ̐V�،��R�[�h�̕t�ԓ��Ɋւ��鎖�����s���Ă��܂������A�����܂ł̐��x�̒蒅�x�������Ă��A�W�҂Ƃ����c�̂����A����26�N6�����A�n�������̎��ƍƓ��l�̎葱���Ƃ��邱�ƂƂ������܂����B���������č���̊W�葱���͂��ׂĂقӂ�ɑ��Đ\�������s�����ƂƂȂ�܂��B���ڍׂ͂��������u�s�����n�����s�c�̘A�����c��v�̊J��
�@�s�����n���̔��s�E���ʓ��̏����ɂ��Ă̏��̌����y�ђ��s����Ƃ��āA�s�����n���s����56�̒n�������c�́i�ߘa2�N4�����݁j�ō\�������A�����c���݂��A��N7���ɋ��c����J�Â��Ă���܂��B �@�������s�s�����n���̔��s�E���ʓ��̏����ɂ��Ă̏��̌����y�ђ��s����Ƃ��āA�s�����n���������Ŕ��s����37�̒n�������c��(�ߘa�V�N4������)�ō\�������A�����c���݂��A��N�R���ɋ��c����J�Â��Ă���܂��B�u�O���[���������s�c�̘A�����c��v�̊J��
�@�O���[���������s�s�����n���̔��s�ɍۂ��ĕK�v�Ȏ����������c�����Ƃ��āA�O���[���{���h���������s����44�̒n�������c��(�ߘa�V�N�R������)�ō\�������A�����c���݂��A�N�S����x�J�Â��Ă���܂��B �@�n���s���Ă���n�������c�̂ɂƂ��āA�����ƌ����L��(IR)�̏d�v���E�K�v�������܂��Ă��܂��B���̂��߁A�S���^�s�����n���s����n�������c�̂��A�ꓯ�ɏW�܂�IR�������s����Ƃ��Ă̍���IR�����{����ƂƂ��ɁA�n�������c�̓����s��IR�����ɂ��Ă̎x�����s���Ă���܂��B����E���C��ւ̍u�t�h��
�n�������c�́A���Z�@�ցE�،���Ћy�ѓ����Ɠ��̗v���ɂ��A�n���ɌW�������̎戵�y�ы��Z�o�ϓ��ɂ��Ă̕���E���C��ւ̍u�t�h�����s���Ă���܂��B�@
�����̎��Ƃ́A������̂ق��A���{���c�y�сi����j�S���s�����U�������̏��������̌�t���āA���{���Ă��܂��B